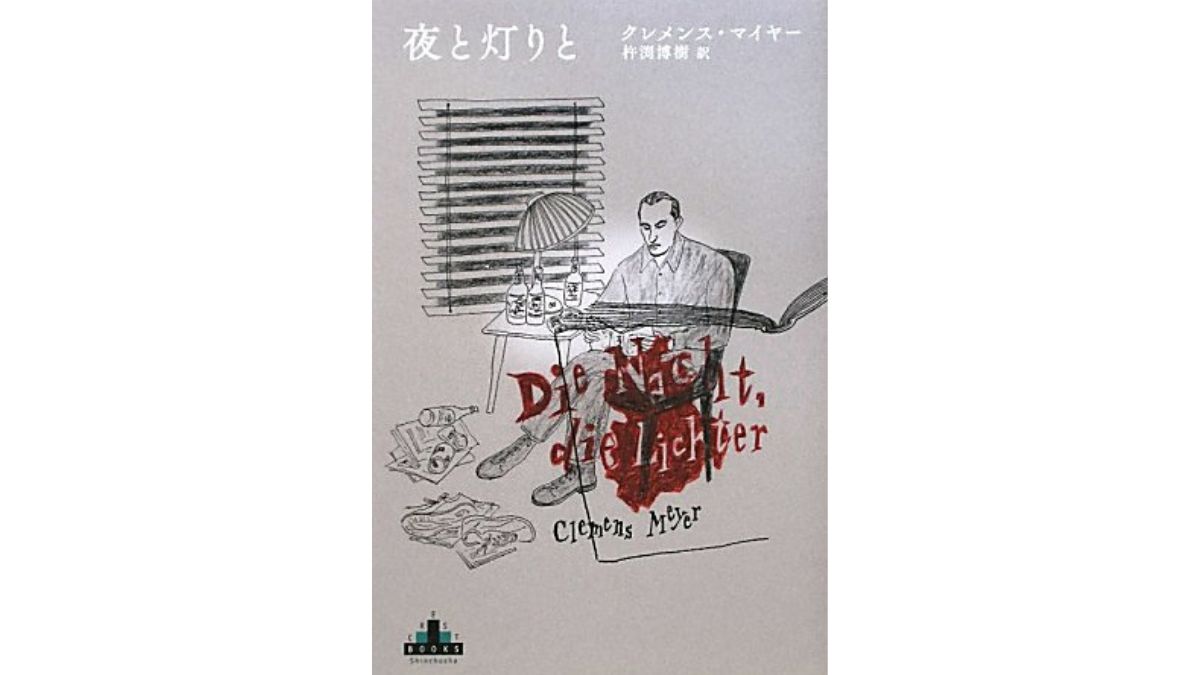夜と灯りと
著者:クレメンス・マイヤー
翻訳:杵渕 博樹
出版社:新潮社
装丁:単行本(239ページ)
発売日:2010-03-01
ISBN-10:410590082X
ISBN-13:978-4105900823
内容紹介:元ボクサーの囚人、夜勤のフォークリフト運転士、ドラッグに溺れる天才画家、小学生に恋する教師、老犬と暮らす失業者、言葉の通じない外国人娼婦に入れ込むサラリーマン-。東西統一後のドイツで「負け組」として生きる人間たちの姿を、彼ら自身の視点から鮮やかに描き出す12の物語。極限まで切り詰めた言葉の積み重ねが、過酷な日常に射すかすかな光を浮き彫りにする。ライプツィヒ・ブック・フェア文学賞受賞。
旧東ドイツの貧困労働者たち
東側で生まれた少年たちは、選択肢を持たなかった。
学校へ行く。働く。酒を飲む。そしてたまに殴るか、殴られるか。
「自由」なんて言葉を知ったのは、壁が壊れたあとの話だった。
そんな時代に、クレメンス・マイヤーは「文学」で生き延びた。
これは、旧東ドイツの”半グレたち”から学ぶ、逆境のサバイバルマニュアルだ。
この本に出てくる男たちは、働いていない。もしくは、働くフリをしている。
借金取りに追われ、女に振られ、酒をあおって転がるように生きている。
だけどそこには、なぜか「誇り」がある。
まともな職に就くこと。社会に適応すること。
現代のおれたちはそれを「安定」と呼ぶけれど、
彼らが生きた街では、それはただの「敗北」に見えたのかもしれない。
だから彼らは、地下で闘った。
ナイフも銃も持たずに、ただ自分の「語り」と「存在」で。
クレメンス・マイヤーはその闘いを、詩のような暴力で描く。
やり直しのきかない世界で、それでも言葉を吐き出すことだけはやめなかった人間たちの姿を、
おれはなぜか、他人事とは思えなかった。
東ドイツはなぜ生まれた?
第二次世界大戦後、ドイツは連合国に分割占領され、冷戦の始まりとともに西側(アメリカなど)と東側(ソ連)の対立が激化。1949年、ソ連の占領地域に社会主義国家「東ドイツ」が誕生した。イデオロギーの対立が生んだ国だった。
生きる苦しみを背負う先にあるもの
だから彼らは、地下で闘った。
ナイフも銃も持たずに、ただ自分の「語り」と「存在」で。
クレメンス・マイヤーはその闘いを、詩のような暴力で描く。
やり直しのきかない世界で、それでも言葉を吐き出すことだけはやめなかった人間たちの姿を、
おれはなぜか、他人事とは思えなかった。
ベルリンの壁はなぜ崩壊した?
1989年、東欧で次々と共産政権が崩れ、市民の不満と民主化の波が東ドイツにも押し寄せた。
体制はもはや国民を抑えきれず、11月9日、東ドイツ政府が出入国の自由を発表。誤解も重なり、数時間後には市民が壁を越え、ベルリンの壁は実質的に崩壊した。体制の終わりは、想像以上に静かで突然だった。
2018年「希望の灯り」として映画化

深夜のスーパーマーケット。
フォークリフトが静かに走り、誰も話さない倉庫で、人々はただ黙々と商品を並べている。
映画『希望の灯り(In den Gängen)』は、旧東ドイツのスーパーマーケットで繰り返される“何も起きない”夜勤の風景を描いている。
だけどこの映画には、どんなアクション映画よりも深い“闘い”がある。
原作はクレメンス・マイヤーの短編集『夜と灯りと』に収められた「通路にて」
監督のトーマス・ステューバーも、マイヤーと同じく旧東ドイツ・ライプツィヒの出身だ。
“あの時代”を知る者たちの目にだけ映る、言葉にしづらい静けさと痛み。
小説に漂っていた、「生きてはいるけれど、もはや何も望んでいない」男たちの気配。
それが映画という形になったとき、より強く、より鋭く、おれの胸に残った。
おわりに
『夜と灯りと』は、歴史的にも二度と訪れることのない「東ドイツの終わり」に立ち会った作家、クレメンス・マイヤーによる作品だ。自分自身と、かつて自分の周りにいた人々を描いているだけに、そこには圧倒的なリアリティがある。深い悲しみの中に、小さな希望がほんのわずかに灯る――そんな余韻を残す、非常に優れた小説だと思う。
装画のデザインも個人的に好みで、ページをめくるたび、手元に置いておきたくなる一冊になった。
労働者として辛い日々をなんとかやり過ごしている人には、ぜひ読んでほしい。きっと、自分のことのように感じる場面に出会い、静かに共鳴する瞬間があるはずだ。
小説を読むとき、その物語が生まれた国や時代の背景を知ることで、より深く理解できると思っている。もちろん、何も知らなくても楽しめるが、多くの作品はその時代や社会情勢の影響を強く受けていて、その背景を知ることで、今を生きるヒントが見えてくることがある。
物語の根っこには、いつも「その時代を生きた人たち」の証がある。だからこそフィクションにも力が宿るし、おれはそんな物語を通して、現代で苦しみ悩み葛藤する人たちに、人生をサバイブするヒントを届けられたらと思っている。